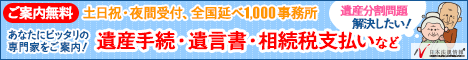この記事は、 相続手続き について興味がある方へ向けた内容となっております。
相続が発生してから、実際に遺産を受け継ぐまでには、いくつかの段階を踏む必要があります。ここでは、相続手続きの流れを解説します。
手順
被相続人(亡くなった方)の相続手続きは、以下のように進めていきます。
- 死亡届の提出
- 遺言書の確認
- 相続人の確定
- 相続放棄・限定承認の検討
- 遺産分割協議
- 相続財産の名義変更手続き
生命保険金の請求や遺族年金、未支給年金の請求等、必要に応じてこれらの手続きも行います。特に、戸籍収集は、昔の戸籍を遡って取得する必要があるため、専門家でも難しいと感じることがあります。
死亡届の提出
故人の本籍地または死亡地の市区町村役場に死亡届を提出します。通常、葬儀社が代行してくれることが多いですが、自身で行う場合は期限(死亡を知った日から7日以内)があるので注意が必要です。

また、提出先は「死亡地、本籍地、住所地のいずれかの市区町村の戸籍・住民登録窓口」ですが、各市区町村ごとに書き方が異なることがあるため、不明点があれば、届出先の窓口に確認するようにしましょう。
遺言書の確認
故人が遺言書を作成していたかどうかを確認します。遺言書には、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3つがございます。順を追って解説致します。
公正証書遺言
公証役場の公証人が、遺言者の意思を確認し、法律に従って作成する遺言書です。公正証書遺言の記録の有無の確認は、遺言書の有無を検索する形で公証役場で行ないます。日本公証人連合会の公式HPにて最寄りの公証役場を調べ、諸手続きを行います。
自筆証書遺言
遺言者本人が、その全文、日付、氏名を自筆で書き、押印(実印でなくても可)することで作成する遺言書です。用紙や筆記具に特に決まりはなく、作成した遺言書は、遺言者自身で保管します。
秘密証書遺言
遺言者が作成した遺言書に署名・押印し、封筒に入れて封をし、その封筒を公証人と証人2名の前に提出して、自分の遺言書である旨を申述する方式です。ワープロなどで作成することも可能で、公証人は遺言書の内容を確認するのではなく、遺言書が存在することを確認します。
また、自筆証書遺言や秘密証書遺言の遺言書が見つかった場合は、家庭裁判所での検認の手続きも忘れずに行いましょう。
相続人の確定
故人の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本などを収集し、誰が相続人となるのかを確定させます。配偶者、子、親、兄弟姉妹など、法定相続人の範囲と順位に従って確認します。相続人の確定には、調査や相続財産目録の作成が必要になります。相続人同士の金銭トラブルに発展しかねない手続きのため、弁護士や行政書士といった法律の専門家と進めていくのが良いでしょう。
🔳相続サポート窓口;日本法規情報
相続放棄・限定承認の検討
相続人は、相続財産を全て受け継ぐ「単純承認」、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も引き継ぐ「限定承認」、一切の財産を引き継がない「相続放棄」のいずれかを選択できます。
単純承認
故人のプラスの財産(預貯金、不動産など)も、マイナスの財産(借金、ローンなど)も、全て無制限に引き継ぐ方法です。特別な手続きは必要なく、原則として相続人が何もしなければ単純承認したとみなされます。
限定承認や相続放棄のような家庭裁判所への申述などの煩雑な手続きが不要なメリットはありますが、単純承認を選択した後で、借金が多額であることが判明しても、原則として撤回することはできないので注意が必要です。
限定承認
相続によって得たプラスの財産の範囲内で、故人の借金などのマイナスの財産を弁済する相続方法です。こちらは、もしプラスの財産よりもマイナスの財産が多かった場合でも、相続人自身の財産で不足分を負担する必要はありません。
ただし、限定承認をする場合は、相続人全員が共同して、相続の開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。また、家庭裁判所での手続きや、相続財産の清算手続きが必要となる点も注意が必要です。
相続放棄
故人のプラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がない方法です。相続放棄をする場合は、相続の開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。相続放棄が受理されると、その相続人は初めから相続人ではなかったものとみなされます。
相続人ではなくなるため、故人に多額の借金があった場合に返済義務を負うことはありませんが、故人に価値のある財産があった場合でも、それらを受け取ることはできません。また、相続放棄をすると、その相続人の次の順位の人が相続人となります。例えば、子が相続放棄した場合、親が相続人になる可能性があります。
以上の事を踏まえつつ、どういう選択をしていくかを検討していくわけですが、これらの選択は、原則として相続の開始を知った時から3ヶ月以内に決定し、必要な手続きを行う必要があるのですが、この期間を「熟慮期間」といいます。熟慮期間内に何も手続きをしなかった場合、原則として単純承認をしたものとみなされます。もし、3ヶ月以内に判断が難しい場合は、家庭裁判所に熟慮期間の伸長の申立てをすることも可能です。
事前予約制ですが、法務局でも相続や遺産分割の相談を受け付けています。
🔳法務局HP
遺産分割協議
遺言書がない場合、または遺言書で全ての財産の分け方が指定されていない場合は、相続人全員でどのように遺産を分割するかを話し合います。全員の合意が得られたら、遺産分割協議書を作成します。
🔳遺産分割協議書(雛形):(金沢相続遺言ヘルプデスクHPより参照)

相続財産の名義変更手続き
遺産分割協議書や遺言書に基づき、不動産、預貯金、株式などの名義を相続人に変更する手続きを行います。その後、相続税の申告と納税を各自治体に納めます。
| 不動産 | 法務局で相続登記 |
| 預貯金 | 金融機関で相続手続き |
| 株 式 | 証券会社で名義書換 |
| 自動車 | 運輸支局で名義変更 |
まとめ

今回紹介したものは、一般的な流れであり、個々の状況によって手続きの順序や必要な書類は異なります。ご自身の状況に合わせ、専門家(行政書士、司法書士、税理士など)に相談しながら進めることを強くお勧めします。特に、期限のある手続き(相続放棄・限定承認、相続税申告・納税)には十分注意しましょう。
この記事以外にも行政書士業務に関する実用的な知識を紹介しておりますのでよろしければご一読頂けると嬉しいです。